
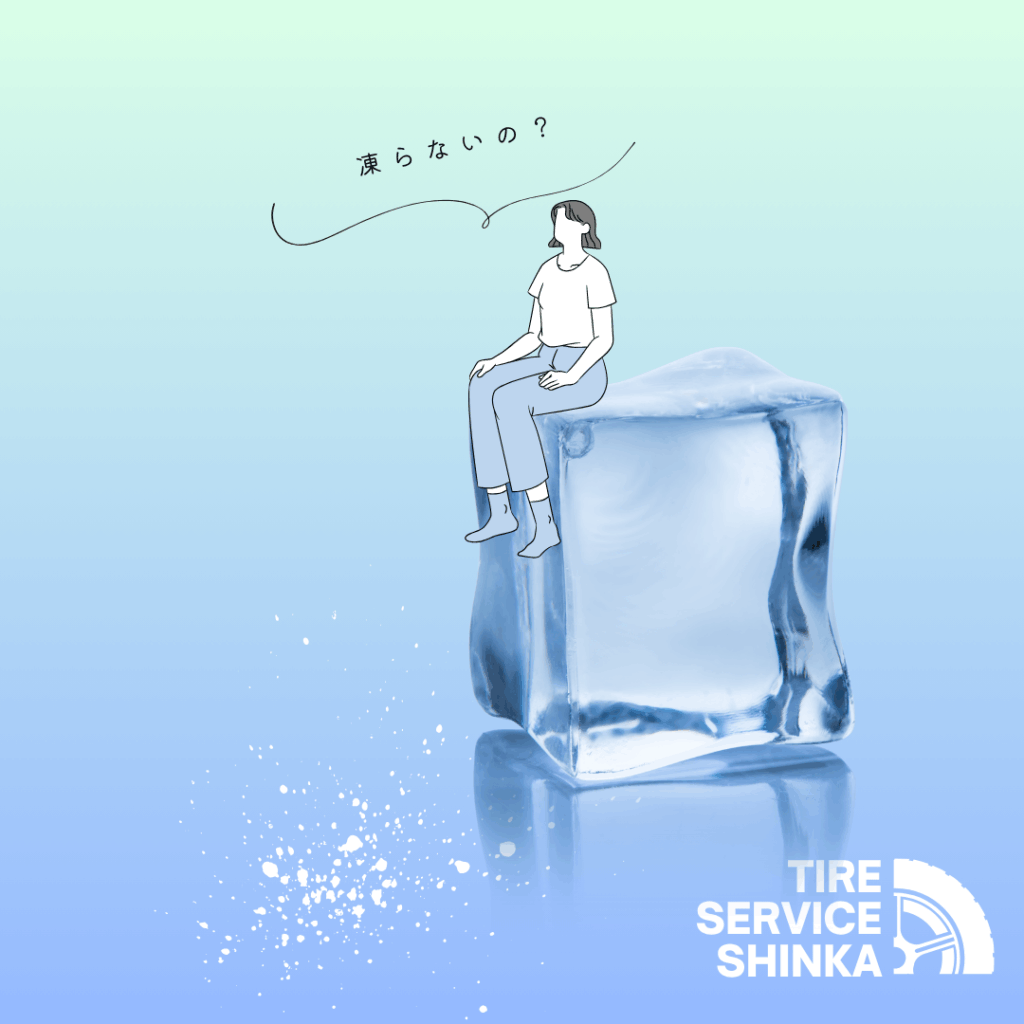
1. 通常の「凍る温度」とは
ふつう、水は0℃で凍る(氷になる)と習いましたよね。
これは「水分子が結晶(氷)として並び始める温度」のようです。
ただしこれはあくまで「標準的な条件下(純水・常圧・不純物なし)」での話です。
2. それでも凍らないことがある理由
実は、条件次第で水は0℃になっても凍らないことがあります。
これを「過冷却(かれいきゃく)」といいます。
● 過冷却とは
不純物がなく、容器の中で静かに冷やされた水は、氷の結晶を作る“きっかけ”がありません。
そのため、0℃を下回っても液体のまま存在できます。
(理論的には -20℃くらいまで凍らないことも!)
3. 過冷却水が凍る瞬間
過冷却状態の水に、ちょっとした刺激(衝撃・振動・ホコリ・氷のかけらなど)が加わると──
一瞬で凍り始め、ボトルの中でサーッと氷が広がる現象が見られます。
実験動画などでもよく見る、「一瞬で氷になる水」はこれです。
4. もうひとつの理由:不純物や塩分
海水や道路の凍結防止剤のように、
水の中に塩やアルコールなどが混ざると、氷の結晶ができにくくなります。
この場合も、凍る温度(凝固点)が下がるため、
「0℃でも凍らない」という現象が起きます。
これを「凝固点降下(ぎょうこてんこうか)」といいます。
5. まとめると…
| 状態 | 原因 | 説明 |
|---|---|---|
| 過冷却 | 結晶の核がない | 0℃以下でも液体のまま(衝撃で一気に凍る) |
| 凝固点降下 | 塩・糖・アルコールなど混入 | 凍る温度自体が下がる(海水・酒・防凍液など) |
6. 身近な例
- 冷凍庫から出したペットボトルの水が、振った瞬間に凍る
- 冬の道路に塩カル(凍結防止剤)をまく
- アルコール飲料が冷凍庫でもカチカチに凍らない
- 自動車のラジエーター液(不凍液)はマイナス数十℃でも凍らない